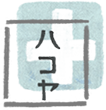定員に達し次第、応募は締め切りとなります
胸中にあるのは、地域のセーフティネットとしての責任感。
深夜、救急車がサイレンを鳴らして駆け込んでくる。当直の小山泰明の胸中にあるのは、「ココが最後の砦だ」との思い。セーフティネットとしての覚悟である。
「助かるか、助からないか、ぎりぎりの状態の患者さんもいます。私は、自分が助けなければいけない責任感がある。最後の砦として何でもやります。」

小山が救急をやろうと決めたのは学生時代の病院実習だった。
理由はシンプルである。「苦しんでいる患者さんを目の前にして、“できない”と言いたくなかったから」だ。それは、中学時代に医師を志すと決めたときの「オールマイティな医者になりたい」という思いにも通じる。
驚いたのは、実際に救急で働き始めて、患者の半数が子供であり、妊婦の来院も多いことだ。救急は小児科も産科も含めた全疾患が対象になる。
「救急医は、何でもできなくてはならない」という思いは、小山の中で確たるものになっていった。
そして2年前、故郷の茨城県に戻り、筑波大学附属病院の救急・集中治療科に籍を置いた。

「ぎりぎりの状態で担ぎ込まれてきた患者さんが、元気に歩いて帰ってくれればハッピー。その笑顔が私のやりがいです。そのために最善を尽くし、専門医のドクターにバトンタッチするのが救急医である私の使命です。」
一方で、どんなに超人的な働きをしようとも、一人の医師では限界があることも確かである。特に県外にあるERメインの病院で修行を積んできた小山の目には、救命のためのシステムづくりが茨城県に必要であると映った。
「医療が高度専門化した結果、救急患者さんのたらい回しの現実が起きています。これからの我々は、社会全体の救急医療体制をマネジメントするメディカルコントロールの役目を果たさなくてはならないと思います。この地域に暮らす患者さんやそのご家族に、“この病院があって助かった”と言っていただくためにも。」
いわば社会全体での、命を救うリレーを行う体制づくりである。
「あらゆる症例と立ち向かうERは医の原点、ICU/小児集中治療はチーム医療の原点、産科救急はコラボ医療の原点。ERからICUへバトンを渡すように、小児科や産科も含めた全ての患者さんを救いたい。」
小山の目指すシステムづくりは、決して簡単なことではない。だが、一人ではなく、志を同じくする仲間がいる。その思いが、小山の背中を強く押してくれる。
目の前の1人だけでなく、手の届かない多くの人のために。
小山が“バトンを渡したい”と言った、ICU側の仲間が、榎本有希である。
「小児集中治療センターにもいますが、救急も診ますし、災害時にはドクターヘリにも乗り込みます。専門は何ですか、と聞かれるのが一番返事に困る。」
榎本はそう目を細める。

榎本が理想の医師像として描いていた姿は、小山のそれと共通している。
「臓器にとらわれずに、身体の全てを診ることができる医者になりたかった。そこで進んだのが小児科でした。」
榎本は都内の小児集中治療の専門施設で2年間学んだ後、「大人の救急も学びたい」と大阪府下の救命センターでも2年勤務した。その後、再び小児集中治療の専門医で勤務した後、母校である筑波大学に戻ってきた。
「子供は生まれつき体の弱い子が多く、医師として無力感を感じることも少なくありません。そんな中で、例えばいったんは心臓が止まってしまった中学生が蘇生して一命を取り留め、なんとか自分の足で歩いて帰れるまでに回復するようなことを経験すると、本当に嬉しく感じます。その中学生は、今、社会人となって元気に働いているそうですよ。」
一方で、最期の瞬間をいかにして子供本人と家族に受け入れてもらうか、という重い課題にも取り組んでいる。子供の死というのは誰にとっても受け入れがたい現実であるが、だからこそ心穏やかに死を迎え入れることはできないかという思いだ。これは今後の榎本にとってのテーマの一つである。
榎本が茨城県に戻る選択をしたのには、理由がある。小児集中治療のシステムを故郷で実現したいと思ったからだ。

先進的な取り組みをしている他県では、集中治療の必要な子供を専門病院に集約するシステムができている。小児科のセーフティネットだ。榎本は、同じシステムを茨城県にもつくりたいと考えているのである。
「以前は、目の前の患者さんを助けたいという思いで走っていました。今はシステムづくりを通じて、患者さんと「1対1」ではなく、「1対n」の関係を築こうと思っています。やりがいは大きいですよ。」
若い研修医や学生たちを指導する時間を意識的に増やしているのも、統括DMAT(災害派遣医療チーム)の資格を持って災害対策に取り組んでいるのも、同じように「1対n」の関係を築くためだ。
若い世代へ、あるいは防災関係者へ、榎本はバトンを渡そうとしているのである。
臨床・教育・研究。その核となる拠点をつくる。
榎本が「救急医療のエリートコースを歩んできた人」と評するのが、教授の井上貴昭である。20余年にわたって海外を含むいくつかの大学病院で救急医としての臨床経験と研究者としての経験を積み、2016年春、母校である筑波大学に戻ってきた。
その動機を問うと、返ってきたのは「フランシスコ・ザビエルの気分ですわ」という答えだった。

「日本有数の救急施設で多くのことを学びました。自分が教えてもらったこと、学んだことを母校に還元したいという思いで帰ってきたんです。」
関西人らしいユーモアあふれる言い回しが、職人のような眼光鋭い風貌とギャップを生み、人を引きつける。
「救急とは、社会の人々にとって実は最も身近な医療です。突然の発熱で病院に駆け込んだ経験は誰にでもあるし、誰だって交通事故に遭う可能性があるのですから。救急医とは、誰もがさらされる危険から救うゲートキーパーのような存在です。」
そして、社会が変われば、救急医療の姿も変わる。井上が救急医をめざした当初は、救急医は交通事故などの外傷患者をしっかり診れる外傷外科が中心であったが、現在では内科の患者も外科の患者も運ばれてくる。子供から高齢者、重症のみならず中等症から軽症に至るまで、ありとあらゆる患者への対応が求められる。
加えてドクターカーやドクターヘリなどの病院前診療や災害医療に至るまで、現在の救急医に求められるニーズは極めて多岐に渡る。ゲートキーパーとして救急医は、そのすべてに対応しなくてはならない。
「“すききらい”なく、どんな患者さんにも対応できる、時代と地域によって異なる要請に応えられる懐深い救急医を育てたいですね。」

これからの若い救急医に伝えたいことは何ですか、との質問に井上は次のような話を始めた。
もう15年以上前であろうか、井上のもとに運び込まれた患者は、工場の機械に腕を巻き込まれて腕がずたずたに損傷した若い男性だった。「なんとか手を落とすことなく、残してあげたい」。その一心で井上は彼の腕の救肢に努めた。
数年後、その男性は自分の子供を連れて井上のもとに現れ、そして子供を井上に抱っこしてもらって写真に収めた。子供の名前には、井上の名前の一文字がつけられていたという。
「“あの時先生がこの腕を救ってくれたから、この子をだっこできるんです”、そう言ってくれました。そんなドラマのような、救急医冥利につきることが本当に起きるんですよ、この世界は。救急医はがんばればがんばるほど、奇跡と感動を味わえるんです。」

井上がこれから若い世代に伝えていきたいのは、そうした救急医療への熱い思いと救急医ならではのやりがいだ。そんな思いに応えて若い人材が集まるようになったら、どんなに素晴らしいことだろう。
「大学は、臨床・教育・研究のすべてに取り組むことができます。私はここを拠点に、臨床はもちろんのこと、教育・研究の交流を図りたい。県内の各施設と連携し、志を同じくする仲間とチームを組んで、救急医療のシステムをつくりたいのです。」
兵庫県出身の井上が遠く茨城県の大学を進学先に選んだのは、高校2年の時、筑波で開かれた科学万博がきっかけだった。
「何もなかった田舎に新しい街ができ、そこに日本中の科学者が集まると聞いて、まさしく夢の国だと思ったんです。」
今、井上はその街に、生命のバトンリレーという新しい夢を描いている。
本原稿にある所属先、役職等の記載は2016年8月31日現在のものです
※本サイトでの募集は終了しております。
採用情報については、公式サイトにてご確認ください。